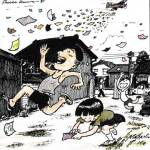あけましておめでとうございます。
本年も『あだち百景』ご愛顧よろしくお願いします。あっ、ついでに林家たけ平もよろしくお願いします。
落語家には年末に新しい黒紋付を誂えて新年を迎えるという人が数多くいらっしゃいます。これは心も新たに「禊」の精神でまた1年、一新した気持ちで過ごそうという表れです。
そして落語家は、お正月、いろいろと縁起を担ぎます。「かつぎや」というお正月ならではの噺がありますが、その中に「あら玉の 年立ち返る朝(あした)より 若やぎ水を汲みそめにけり これはお年玉」という名セリフがあります。是非、今度、聴いてみてください。
年末に「お年玉」を支度しておくというのは我々の恒例行事であります。普段、寄席で働いている「前座さん」(修行中の落語家)や、「お囃子さん」(寄席芸人の出囃子を弾く人)に配ります。
元日、寄席に楽屋入りすると、前座さんから「おめでとうございます」と、挨拶を受けます。普段は「おはようございます」と言われますが、その年に初めて会う場合には、「おめでとうございます」と言うのが慣例となっています。これが「お年玉」を、挨拶してくれた前座さんに配る合図になります(笑)。
私も前座の頃、経験がありますが、新年早々のご挨拶で、いつものように「おはようございます」とうっかり言ってしまうと、師匠によっては、「はい、おはよう」と返してくださるだけで、お年玉が支給されないこともあるのです。だから、必死に「おめでとうございます」と言い続けた記憶があります(笑)。
前座さんにもなっていない、いわゆる「見習い」の方にもお年玉をお配りします。まだ芸名も付いていない見習いさんも、師匠の鞄持ちとしてお正月の寄席に来ます。顔も初めて見るし、名前さえ分からないのですが、その人たちにもお年玉はちゃんと配ることになっています。「おめでとうございます」と言われると、落語家は条件反射的にお年玉を渡してしまうのです。
何年か前のことですが、駅のホームで青年が「おめでとうございます!」と声をかけてきたことがあります。全く知らない人でしたが、「ああ、どこかの見習いさんかな?」と思って、私も「おめでとう」と言ってお年玉を差し上げたことがあります。
それから数年経ちますが、その後、その青年を楽屋で見たことがありません(笑)。今から思えば、落語ファンの若いお客様が落語家を見つけてご挨拶してくれた、というのが真相だったような気がします…。
「返してくれ〜! お年玉〜!」。良い子の皆さんは、真似しないでくださいね。我々、落語家。お正月は、こんなことにも気をつけながら生活しています。
本年もどうぞよろしくお願いします。